興味消費
関連コンテンツ

2024年中国デジタル文化産業における若者の興味消費行動の分析
- 翻訳
- W11
- 興味消費
- Tmall(天猫)
- Alipay(支付宝)
- 消費
中国で発表した最新の「2024年中国電子商取引「ダブルイレブン」消費ビッグデータモニタリングレポート」によると、2024年に「ダブルイレブン」活動に参加する主な消費者は26~29歳の若者であり、比率34.1%を占める「ダブルイレブン」 「イベント期間中に購入数の多かった商品カテゴリーTOP3を分析しました。また、「楽しい消費」や消費階層化などの需要動向と消費体験について解説しました。
2025/01/151

中国アウトドア市場:キャンプ市場の成長とトレンド
- 特集
- 興味消費
- マーケティング
- ECモール
- トレンド
- アウトドア
- キャンプ
- 消費
中国のアウトドア用品市場は、2025年までに核心市場規模が2483.2億元、関連市場を含めると14402.8億元に達すると予測されています。この成長に伴い、購入方法もさらに多様化し、消費者のニーズに合わせた柔軟な販売戦略が求められています。
2025/01/081
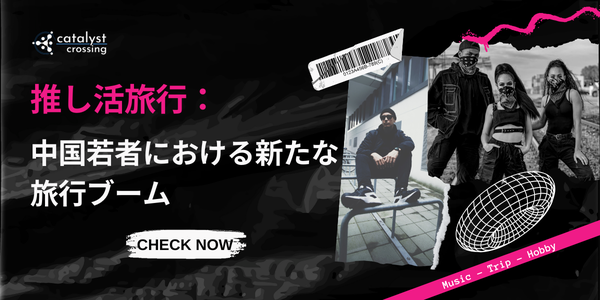
推し活旅行:中国若者における新たな旅行ブーム
- 特集
- 興味消費
- 旅行・観光
近年、「推し活旅行」は中国の若年層で急速に人気を集める新しい旅行スタイルとなっています。従来の観光旅行とは異なり、推し活旅行は単なる観光スポットの見学にとどまらず、アイドルと同じ空間を共有することで得られる感情的なつながりが重視されます。一線都市である北京や上海のコンサートから、地方都市でのファンミーティングや音楽フェスティバルに至るまで、推し活旅行は中国各地で広まりを見せ、都市部には大きな経済的効果をもたらしています。
2024/12/311

急成長する中国のウインタースポーツ市場の分析
- 特集
- 興味消費
- マーケティング
- トレンド
- 旅行・観光
中国ウインタースポーツ市場は、「最後の巨大市場」と呼ぶにふさわしい成長を遂げています。地理的な近さや文化的な親和性を強みに、日本企業がこの成長市場でどのように活躍していくのか、今後の展開が注目されています。
2024/12/251
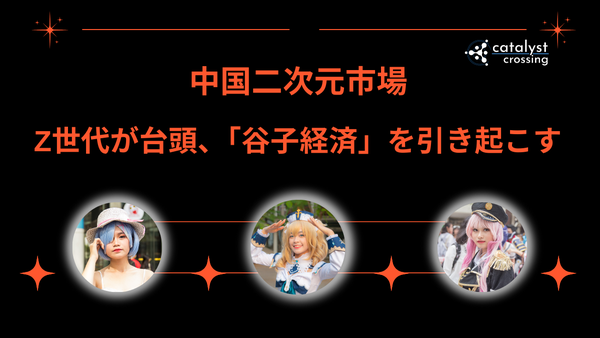
中国二次元市場:Z世代が台頭、「谷子経済」を引き起こす
- 特集
- 興味消費
- トレンド
- 消費
- エンタメ
- Z世代
中国の二次元市場は、Z世代を中心とした若年層の強い支持を受け、急速に拡大しています。今後、高品質なコンテンツの提供とIP価値の最大化により、市場の更なる成長が見込まれます。企業はZ世代の心を捉える戦略を展開することが成功の鍵となるでしょう。
2024/12/201

中国の雪スポーツ産業のデータ分析: 52.52%の雪スポーツ愛好家がフィギュアスケートイベントに参加
- 翻訳
- 興味消費
- トレンド
- 消費
- エンタメ
北京五輪の成功により、中国では雪スポーツの人気が高まって普及しているとわかりました。中国政府は雪スポーツを積極的に推進し、国民の参加度を促進させており、消費規模は増加し続けています。また、消費者行動の面では、フィギュアなどの愛好家の数が増えていると考えられます。
2024/12/171
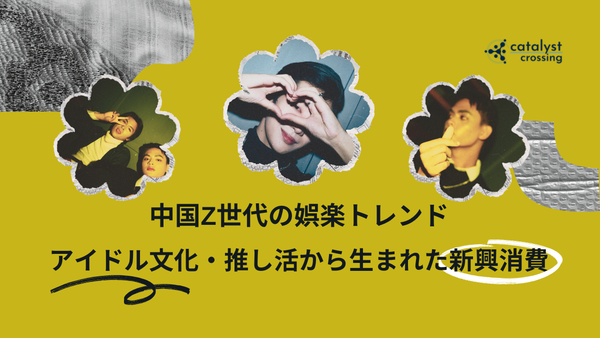
中国Z世代の娯楽トレンド:アイドル文化・推し活から生まれた消費
- 特集
- 興味消費
- トレンド
- エンタメ
中国のアイドル産業の急速な発展に伴い、中国でのアイドル育成は急速に発展しています。調査データによると、中国でのアイドル・推し活に対する消費に後悔がないと表明しています。そこで、ファンエコノミーの発展に伴い、中国でのアイドル育成は急速に発展しているほか、バーチャルヒューマンの誕生と発展により、アンカーやアイドルなどを促進させ、今の中国Z世代の新興消費のトレンドとなっています。
2024/12/111

中国「悦己消費」:新興消費スタイルが誕生!
- 特集
- W11
- 興味消費
- インバウンド
- トレンド
- EC
- 消費
経済社会構造の変化に伴い、新たな消費トレンドが出現しています。中国で新たな消費トレンド「悦己消費」が若年層の生活態度となっており、自分を幸せにし、より良い人生経験を得るという目的を持った消費スタイルを持つ若者が少なくありません。本記事では、海外旅行やダブルイレブン(W11)期間における、中国の新興消費トレンドといった「悦己消費」について見てみましょう!
2024/12/061

【邦人NAVI】名創優品が“興味先導消費”を軸に1万店計画、日本イメージ払拭、成長戦略に脚光
- ニュース
- 興味消費
- 消費者行動
- 邦人NAVI
生活雑貨チェーンを展開する名創優品(MINISO、メイソウ)は「興味先導消費」を軸に成長戦略を展開している。積極的な出店攻勢を通じて市場拡大を図り、消費者の興味を引きつける商品や体験を提供することで、競争優位の確立を目指す。グローバル市場におけるブランド価値を高めつつ、2027年までに総店舗数1万店の達成を目標に据える。
2024/11/121

2024年中国若者の趣味に関するレポート
- 特集
- 興味消費
- 消費者行動
中国の「Soul App」がZ世代に対し趣味や興味に関するアンケートを実施した。このアンケートは3481名が参加し、その中の8割がZ世代で構成されている。アンケートでは、若者の趣味、趣味に対する消費傾向などをアンケート形式で回答収集している。本文では、中国若者の趣味への消費傾向については見てみましょう。
2024/11/081

中国における大学生の消費トレンド
- 特集
- タオバオ(淘宝)
- 興味消費
- トレンド
- 消費
- Douyin(抖音)
- ピンドゥドゥオ(拼多多)
日本政府観光局(JNTO)が10月16日に発表した訪日中国人のデータにより、中国訪日観光客のなか、若者のほうが人数が最も多いとわかりました。2024年の中国大学生の年間消費規模は約8,500億元と推定されており、莫大な消費余地があります。本文では、中国大学生の消費トレンドおよび消費変化傾向について見てみましょう。
2024/10/291

中国の若者によるフィットネス業界の消費トレンド:前払い式消費の冷え込み、単発消費モデルの台頭
- 特集
- 興味消費
- 健康・ヘルスケア
- 消費
近年、消費観念の変化に伴い、中国の若者は前払い式消費に対する警戒心を高めており、単発消費モデルが急速に台頭している。ジムの会員カードや他の前払い式サービスに関しても、若い消費者はより柔軟で個別化された消費スタイルにシフトしている。
2024/10/181

【邦人NAVI】「ギネス登録」の屋内スキー場が上海で正式開業、深圳でも“世界最大”施設が建設中
- ニュース
- 興味消費
- 上海
- 邦人NAVI
上海臨港新エリアに誕生した「耀雪冰雪世界」は、総面積9万8,828平方メートルを誇り、世界最大の屋内スキー場として9月6日にギネス認証も受けた。初心者から上級者まで楽しめるゲレンデのほか、ウォーターパークも併設され、オールシーズンで多彩なアクティビティが楽しめる。
2024/09/181

中国市場┃甘粛博物館が麻辣燙人形を販売、甘博文化創造産業はもう次のステップへ
- 翻訳
- 興味消費
- マーケティング
- トレンド
- 消費
甘粛省の郷土料理である麻辣燙が博物館の文化財と響き合い、麻辣燙人形は伝統的な地元食と現代的な要素を巧みに結びつけており、地域の特徴を保ちながら、現代の美的トレンドにも適合しています。甘粛省博物館の成功はほかの文化機関にとっても参考になり、文化資源の徹底的な調査や現代社会に合った文化的要素の発見が求められています。
2024/08/191

【邦人NAVI】上海国際映画祭、いよいよ明日開幕!銀幕に輝く注目の日本作品、チケット入手法は?
- ニュース
- 私域流量
- 興味消費
- 上海
- 邦人NAVI
第26回上海国際映画祭が6月14日に開幕する。日本からは61作品が出品され、日本映画ウィークにも注目が集まる。一方、日本国際交流基金がオンライン映画祭「JFF ONLINE 2024」を開催している。『ゴジラ-1.0』や『君たちはどう生きるか』のオスカー獲得で世界が熱い視線を注ぐいま、日本の映像コンテンツはよりいっそうの飛躍を遂げる時機を迎えている。
2024/06/141

中国市場┃中国EVにおける装備競争
- 特集
- 興味消費
- 消費
中国のEV車に搭載されている装備はまだまだこんなものではなく、冷蔵庫をはじめ、ゲーム、マッサージチェア、化粧台、等々、走る端末から走る居住空間にまで進化しようとしている。そんな中国の激しい競争の中ではもちろん淘汰されていくメーカーも多く、この前まで勢いのあった新しいメーカーが急に倒産するようなことも実際にあった。
2024/06/121

【邦人NAVI】香港と上海でドラえもん旋風!テーマ列車とバスが出発進行!
- ニュース
- 興味消費
- 交通
- 邦人NAVI
日本では藤子・F・不二雄生誕90周年を記念したイベントで盛り上がりを見せているという。一方、中国での人気の的はもっぱらドラえもんだ。香港では25日にドラえもんをテーマとした世界初のドローンショーが行われ、夜空を華やかに演出した。さらにテーマ列車も登場、世代を超えて市民の関心を集めている。一方、上海では新作映画の公開に合わせて「ドラえもんバス」の運行が始まった。
2024/06/061

【邦人NAVI】数字が紡ぐ中国の商戦、『520』の次に来る熱狂イベントは?
- ニュース
- W11
- 興味消費
- 消費
- 消費者行動
- 邦人NAVI
中国では伝統と現代が入り混じる“ショッピングイベント”で1年が埋め尽くされているかのようだ。いまや日本人の間でもおなじみとなった「双11節(ダブルイレブン)」、それに「618」といった電子商取引のプラットフォームが主催するもの以外にもユニークな記念日がある。「520」もその代表的なものの一つだ。
2024/05/221

中国消費┃中国で起こるピアノ販売不振の背景
- 特集
- 興味消費
- マーケティング
- 消費者行動
実はここ数年、中国ではピアノの販売・生産減少というニュースが相次いで煽り、今年2024年も非常に厳しい年となりそうだ。以前、中国は世界でピアノを習う子供の8割が集中するとされるピアノ大国であり、各国のメーカーにおける主戦場となっていた。
2024/05/141

中国消費┃中国の購買行動における背景とプロセス
- 特集
- タオバオ(淘宝)
- 興味消費
- RED(小紅書)
- Tmall(天猫)
- 消費者行動
- Douyin(抖音)
- ピンドゥドゥオ(拼多多)
中国における購買行動について、インターネット上では「中国ではインターネット上での購買がほとんど・・・」という様な情報が多く出ているものの、実際の背景についてはなかなか中国にいないと掴めないものである。現状のオンライン購買拡大の要因や最近の購買行動プロセスについて、現地にてわかる背景や要素についてご紹介したい。
2024/05/091

catalyst-crossing とは
海外経済情報の総合メディア
現地のリアルな情報をリアルタイムでお届けします